
ご安全に!瑠璃坊主です
先日の「Google Cloud Next Tokyo ’25」では、Googleの最新技術が多くの企業のビジネスをどう変えているのか、具体的なデモンストレーションを通じて紹介されました。AIが単なるツールではなく、ビジネスの「パートナー」として活躍する未来が、もはや現実のものになりつつあることが示されました。
この記事は、Google Cloud Next Tokyo ’25の基調講演の中の事例を紹介をしています。まだこの記事を読んでいない方はこちらから読んでください>>>【Google Cloud Next Tokyo ’25議事録】AIが拓く未来の働き方:最先端の技術を発表

今回は、ミクシィ、メルカリ、動画広告制作、博報堂、そして札幌市役所といった日本を代表する5つの事例から、AI活用の最前線を見ていきましょう。
ミクシィ:AIが創造性を解き放つ
スマートフォンゲームやSNSで知られるミクシィ社は、Googleが提供するAIプラットフォーム「Google Agent Space(グーグル・エージェント・スペース)」をいち早く導入した企業のひとつです。同社は、AIを活用して「経営や管理といったクリエイティブではない業務」を自動化し、社員が「創造的な仕事」に集中できる環境を目指しています。
Google Agent Spaceとは、複数のAIエージェント(特定のタスクを自律的にこなすAI)をまとめ、組織全体で活用できるようにするプラットフォームのことです。例えば、社員が「来月の新企画のマーケティングレポートを作成して」と指示するだけで、AIが能動的に複数のシステムと連携し、タスクを完了させてくれます。
講演では、マーケティングコンテンツをAIが自動で作成するデモが披露されました。
- データ収集: AIエージェントが、社内の過去のコラボレーションデータや、これまでのマーケティングキャンペーンの結果、さらには外部の市場トレンド情報などを横断的に収集・分析します。
- アイデア創出: 分析結果をもとに、AIが「若者向けの新しいキャラクターコラボ」や「SNSで流行中のトレンドを活用したキャンペーン」など、具体的な企画アイデアを複数提案します。
- コンテンツ生成: 提案されたアイデアに沿って、企画書に使うイメージ画像や、SNS投稿用の動画素材など、クリエイティブなコンテンツを自動で生成します。
- レポート作成: 最終的に、収集したデータ、アイデア、生成したコンテンツをまとめ、企画書形式のレポートを自動で作成します。
この仕組みにより、これまで人間が数週間かけていた企画・制作のプロセスが劇的に短縮され、社員はより質の高いアイデアを考えることに時間を使えるようになります。ミクシィは、AIによって「非クリエイティブな業務」をなくし、社員が「楽しい」と感じられる仕事に集中する未来を目指しているのです。
メルカリ:AIが24時間365日顧客をサポート

フリマアプリ「メルカリ」は、AIを「サービスをより良くするための中間技術」と位置づけ、特にカスタマーサポート領域での活用を進めています。
メルカリのカスタマーサポートは、多岐にわたる問い合わせに対応しなければなりません。例えば、商品の発送、受け取り、取引のトラブルなど、内容は複雑かつ多岐にわたります。さらに、海外のユーザーも増えているため、多言語でのサポートも大きな課題でした。メルカリがAIで解決したいと考えているのは、以下の3つの課題です。
- 自己解決の促進: ユーザー自身が、AIのサポートで問題を解決できるようにする。
- 即時対応と連携: 問い合わせに素早く対応し、必要に応じて担当者へスムーズに引き継ぐ。
- オペレーターの支援: オペレーター(お客様対応の担当者)の負担を減らし、より質の高いサポートを提供できるようにする。
デモでは、新しいAIチャットサポートシステムが紹介されました。ユーザーがアプリから問い合わせをすると、AIエージェントが配送状況の追跡ページを案内するなど、よくある質問に即座に答えてくれます。このAIは、取引データと連携しているため、お客様個別の状況を理解した上で適切な情報を提示できます。
もしAIでは解決できない場合、担当者へ引き継がれますが、その際にAIが「問い合わせ内容」や「お客様の感情」を要約してくれるため、担当者はすぐに適切な対応を始められます。また、AIは回答の候補を提案してくれるため、オペレーターは回答を考える時間を大幅に短縮でき、より多くの顧客に対応できるようになります。
このシステムは多言語に対応しており、AIが言葉の壁をなくすことで、世界中のユーザーを一つの場所からサポートできるようになります。メルカリは、AIを活用して「いつでも、誰でも、適切なサポートを受けられる」世界を目指しているのです。
動画広告の未来:AIが企画・制作を高速化
広告業界のデモンストレーションも注目を集めました。Googleの「シナリオビルダー」というAIツールは、動画広告制作の課題を一気に解決する可能性を秘めています。
これまでの動画広告制作は、企画、提案、撮影、編集といった多くの工程を経て、完成までに数週間から数カ月かかり、その間にビジネスチャンスを逃すこともありました。このツールは、そのプロセスを劇的に短縮します。
デモでは、新しいスムージーの動画広告を作る様子が披露されました。
- キャンペーン情報の入力: 広告担当者が、製品名や概要、ターゲット層(例:20代後半から40代のビジネスパーソン)といった情報をAIに教えます。
- コピーとコンセプトの生成: AIがターゲットに響くキャッチコピーを複数提案。さらに、それらのコピーを元に、複数のコンセプト(例:「忙しい日常を彩るスムージー」や「美と健康を意識する人へ」)とストーリーボード(絵コンテ)を同時に生成します。通常、一つ作成するのに数日かかる作業が、このツールを使えば即座に行えます。
- 詳細のカスタマイズ: 提案されたストーリーの一部を「東京の一軒家」から「東京の高層オフィスビル」へと変更するなど、細かなカスタマイズも簡単に行えます。
- 動画生成: 最後に、生成された絵コンテを元に、直接動画を生成します。デモでは、作成された動画が実際に再生され、完成度の高さが示されました。
このツールを使えば、通常数週間かかる企画作業が、たった数分で完了します。生成された動画は、本格的な撮影のたたき台として使うこともできますし、そのままSNS広告として配信することも可能です。これにより、マーケターは「アイデア出し」と「意思決定」に集中できるようになるのです。
博報堂:AIをパートナーと捉える新しい働き方

広告代理店の博報堂は、AIを「人間の創造性を拡張するパートナー」と捉えています。AIが「正解」を出すのではなく、社員がAIと対話することで、新しいアイデアや気づきを得られるようにするという考え方です。
この考え方に基づき、博報堂は全社員にAIアシスタントGeminiを導入しました。
- 「逆メンター制度」: 若手社員が役員にGeminiの使い方を教えるという、ユニークな取り組みが自発的に生まれました。これにより、社内にAI活用の熱が広がり、全員がAIを使いこなそうという意識が高まりました。
- 導入効果: わずか1カ月のトライアル期間で、9割の社員が継続利用を希望するほど、業務に浸透しました。例えば、企画会議でGeminiを「壁打ち相手」として活用するケースが生まれています。
- プランナーが「次のキャンペーンのターゲット層に響くキーワードを考えて」と問いかける
- Geminiが社内データやトレンド情報から関連性の高いキーワードを複数提示する
- プランナーはAIの答えをそのまま使うのではなく、「なるほど、このキーワードとこのキーワードを組み合わせたら、新しいコンセプトが生まれるかもしれない」といった、人間にしかできない発想につなげていく
博報堂は、AIとの共創によって、社員の意識と行動を変革し、クライアントのAI導入やマーケティング支援も強力に支援しています。AIを「道具」として使うのではなく「相棒」として向き合う、新しい時代の働き方を示してくれました。
札幌市役所:AIで「お役所仕事」をクリエイティブに
最後は、札幌市役所です。約1万6千人の職員が働く巨大な組織が、AIによってどのように変わったのか、その事例が紹介されました。
これまでの市役所では、部署ごとに業務が分断され、ファイルがメールに何度も添付されてどれが最新版かわからなくなるなど、非効率な点が課題でした。これにより、市民サービスにも遅れが生じる可能性がありました。
この課題を解決するため、札幌市は「Google Workspace(グーグル・ワークスペース)」を全庁的に導入しました。Google Workspaceとは、Gmailやドキュメント、カレンダーなどがセットになった、Googleのオフィスツールのことです。
この導入で、市役所の働き方は大きく変わりました。
- 組織の壁を撤廃: 部署の縦割りを越えて、課題ごとにチームを組めるようになりました。例えば、「高齢者支援」や「子育て世代への情報提供」といったテーマごとに職員が集まり、部署の垣根を越えて情報共有や議論ができるようになったのです。これにより、意思決定が圧倒的に速くなりました。
- 会議の質が向上: 会議の目的が「報告する場」から「創造する場」に変わりました。参加者は事前に資料を共有し、会議中はGeminiを使って議事録を自動で作成。これにより、より深く議論に集中できるようになりました。
- オープンな文化: 誰もが情報にアクセスできるようになったことで、透明性が高まり、新しいアイデアも生まれやすくなりました。職員が発見した市民の課題を、部署の枠を超えて共有し、解決策を議論するといった、創造的な仕事が増えたのです。
札幌市は、AIやクラウド技術を導入することで、単なる業務効率化だけでなく、「お役所仕事」をよりクリエイティブで、市民にとって価値のある活動に変革しようとしているのです。行政のデジタル化は、市民サービス向上に直結する重要な取り組みであり、その成功事例として大きな注目を集めています。
まとめ
今回紹介された5つの事例は、AIが単に業務を効率化するだけでなく、私たちの働き方、そして組織の文化そのものを変える力を持っていることを示しています。ミクシィのように「創造性」に、メルカリのように「顧客体験」に、そして札幌市のように「行政サービス」に、AIが貢献しているのです。
これらの事例は、AIの活用がもはや一部の先進的な企業の話ではなく、あらゆる業界で当たり前になりつつあることを物語っています。未経験からIT業界を目指す瑠璃坊主さんにとって、これらの動向は大きなヒントになるはずです。AIを使いこなすスキルは、これからのキャリアを考える上で非常に重要になってきますよ。

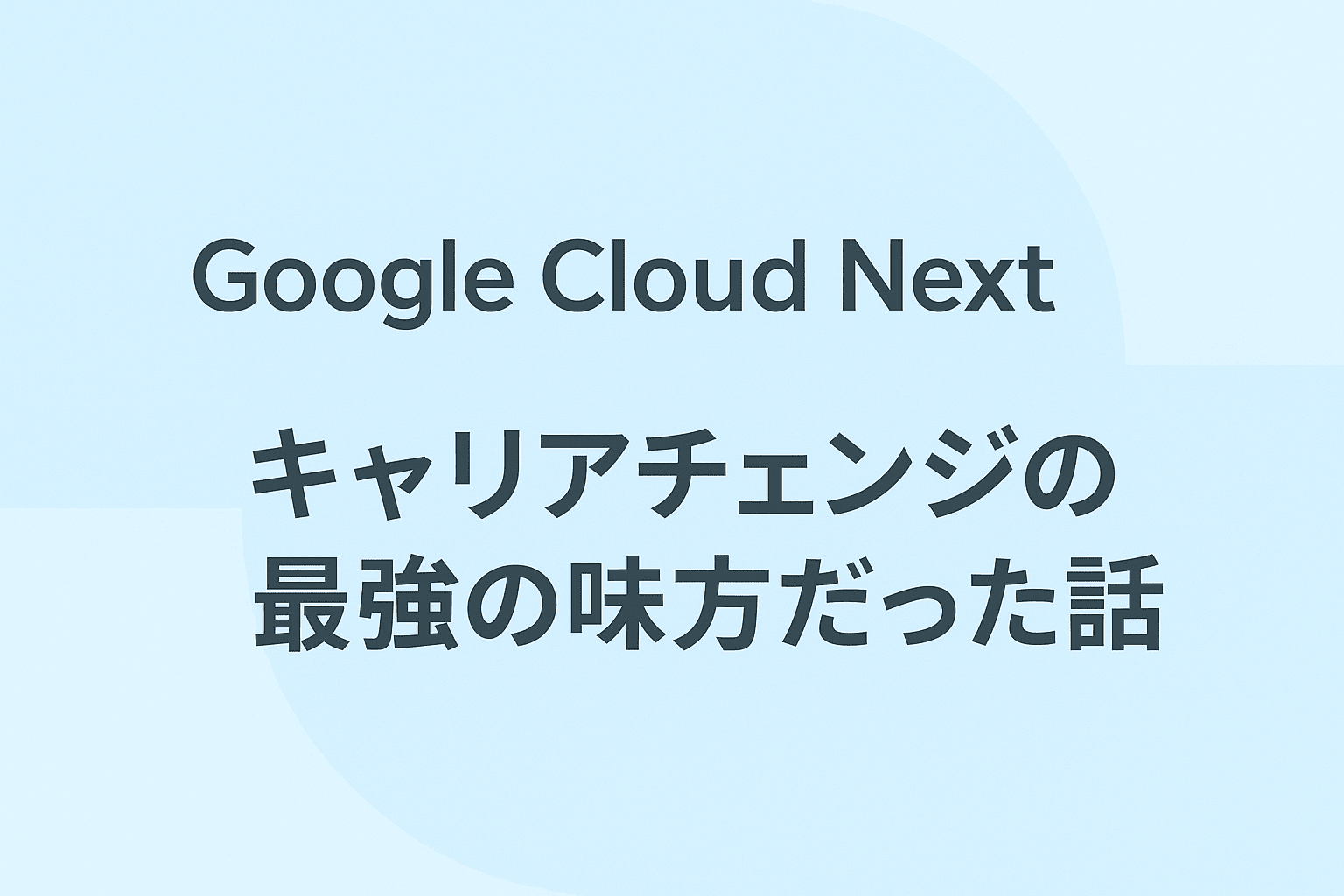
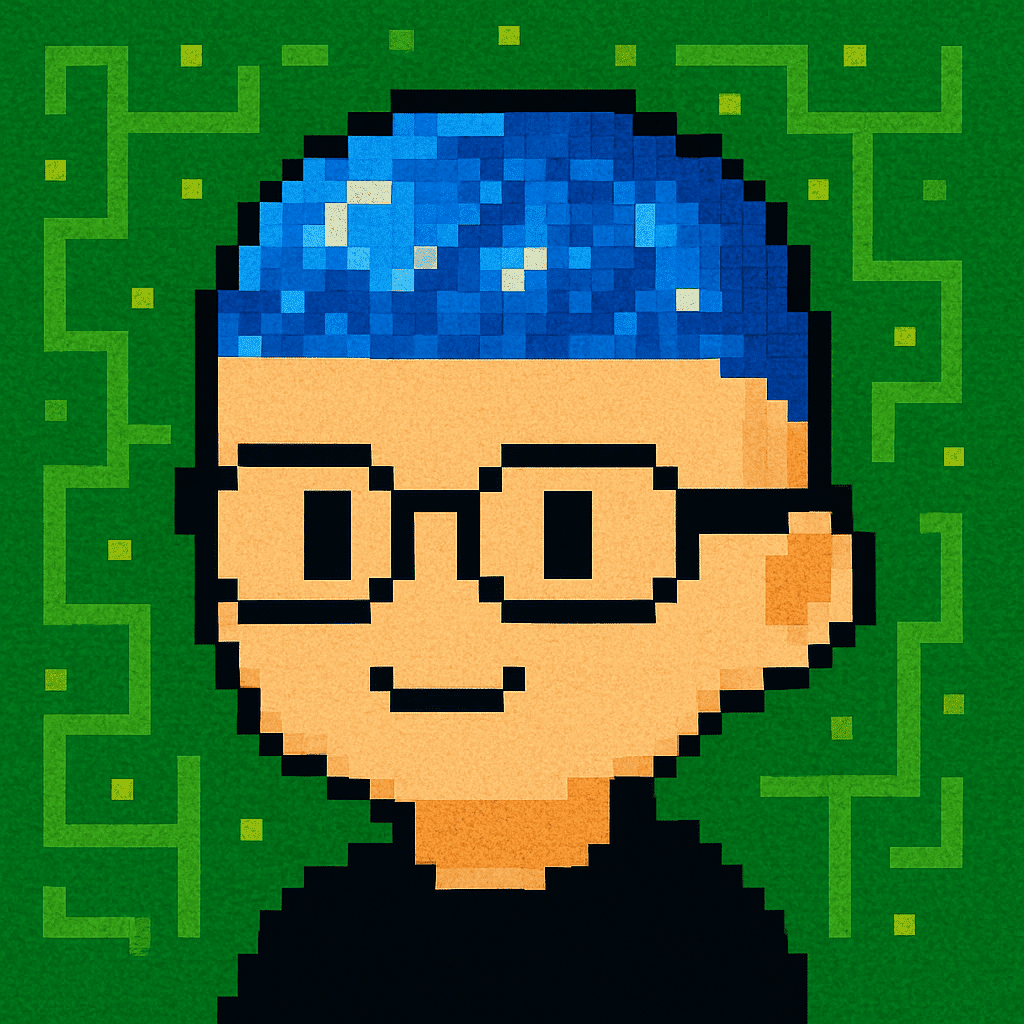

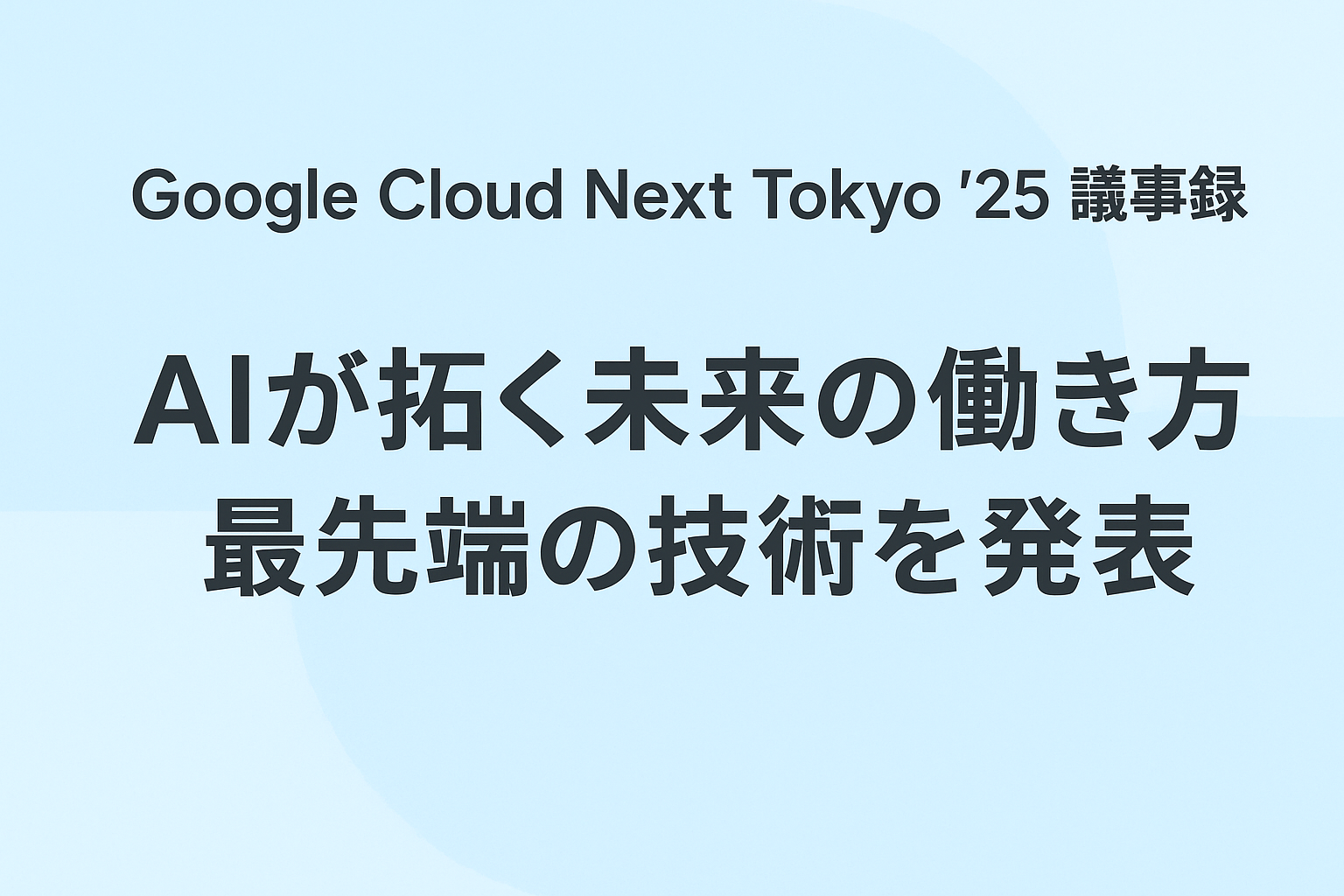
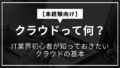
コメント