
皆さん、ご安全に!瑠璃坊主です。
前回は、クラウドの利用形態である「パブリッククラウド」と「プライベートクラウド」について解説しました。クラウドの便利な仕組みが少しずつ見えてきたでしょうか?
前回の記事はこちら↓
【初心者向け】パブリッククラウドとプライベートクラウドの違いとは?
今回は、Udemyの講座「初めてのクラウドの入門-ビジネスパーソンがクラウドコンピューティングの基本を学び、ビジネスへの活用方法を知る」で学んだ「クラウドの安全性(セキュリティ)と信頼性」について、皆さんと一緒に考えていきたいと思います。
「クラウドって、自分の大事なデータを預けても本当に大丈夫なの?」
「自社の機密情報を、他社のサーバーに置いておくなんて不安だ…」
そう感じている人も少なくないと思います。結論から言うと、多くのケースで、クラウドはオンプレミス{自社でサーバーやネットワーク機器を保有し、管理するシステム形態のこと}よりも高い安全性を確保できると考えられています。
なぜそう言えるのか、そしてどんなリスクがあるのかを、一つずつ見ていきましょう。
クラウドに潜むリスクの種類と対策
どんなに優れたシステムでも、リスクを完全にゼロにすることはできません。クラウドも例外ではなく、いくつかのリスクが存在します。それらのリスクを事前に知り、適切に対策を講じることが重要です。
1. 事業者側のトラブル
利用しているクラウド事業者のシステムで、予期せぬトラブルが発生し、サービスが一時的に停止したり、最悪の場合、データが失われたりする可能性があります。
対策: このリスクに備えるためには、「冗長化」と「バックアップ」が鍵となります。
- 冗長化{システムを二重化・多重化すること。片方のシステムがダウンしても、もう片方でサービスを継続できるようにする仕組み}: 大手クラウド事業者は、世界中にデータセンターを分散して配置しています。例えば、東京のデータセンターで大規模な障害が起きても、大阪のデータセンターに瞬時に切り替えることで、サービスを継続できるようにしているんです。これは、自社で複数のデータセンターを運用することが難しい中小企業にとって、非常に大きなメリットとなります。
- 定期的なバックアップの取得: 万が一の事態に備え、データのバックアップを定期的に取得しておくことが重要です。クラウドサービスには、データの自動バックアップ機能が標準で備わっていることが多いため、これを活用することで手間をかけずにデータの安全性を高めることができます。
2. 通信時のリスク

クラウドサービスは、インターネットを通じてアクセスするため、通信時に悪意のある第三者から情報を盗み見られたり、なりすましをされたりするリスクがあります。これを「中間者攻撃{通信している二者間(例えば、あなたのパソコンとクラウドのサーバー)に第三者が割り込み、情報を盗聴・改ざんするサイバー攻撃}」と言います。
対策: このリスクを回避するために、通信を「暗号化」します。
- 暗号化: データを他人に読み取れないように、ルールに基づいて変換することです。皆さんが普段見ているWebサイトのアドレスが「http」ではなく「https」になっているのは、この暗号化が行われているためです。「https」の「s」は「Secure(安全な)」を意味しており、通信が暗号化され、安全に情報がやり取りされていることを示しています。重要な個人情報などを入力する際は、必ずアドレスが「https」になっているか確認する癖をつけましょう。
3. 人為的なミス
どんなにシステムが完璧でも、それを管理・操作するのは人間です。設定ミスや操作ミスといった「ヒューマンエラー」でシステムに障害が発生するリスクは避けられません。
対策: ヒューマンエラーを減らすための対策はいくつかあります。
- 作業者のスキルアップ: 研修や資格取得を通じて、作業者のITスキルを向上させることは基本中の基本です。
- 事前の検証: 本番環境に適用する前に、テスト環境で十分に動作検証を行うことも重要です。
- 自動化を進める: 繰り返し行うような作業は、自動化ツールを使うことで、手動での操作ミスをなくすことができます。クラウドサービスには、このような自動化ツールが豊富に用意されているので、積極的に活用することが推奨されています。
4. サービスの継続性
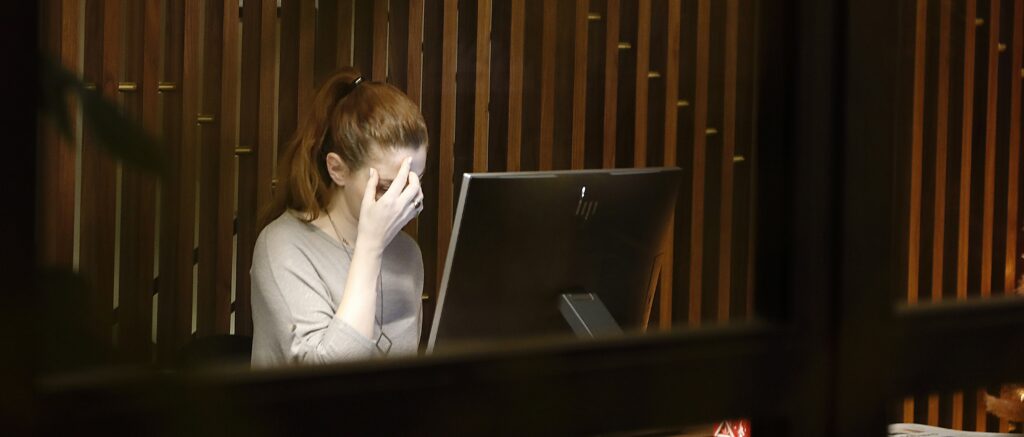
利用しているクラウドサービスが、事業者の都合で突然終了してしまうリスクです。
対策: このリスクを回避するためには、利用するサービスを慎重に選ぶことが大切です。
- 世界的な大手サービスを利用する: AWS(Amazon Web Services)、Azure(Microsoft Azure)、**GCP(Google Cloud Platform)といった世界的な大手サービスは、多くの企業が利用しており、すぐにサービスが終了する可能性は極めて低いと考えられます。もしサービスが終了する場合でも、事前に十分な告知が行われるのが一般的です。
- マルチクラウドを利用する: 一つのクラウドサービスに依存するのではなく、複数のクラウドサービスを組み合わせて利用する「マルチクラウド」という考え方もあります。これにより、万が一あるサービスが終了しても、別のサービスで業務を継続できる体制を整えることができます。
🌍なぜクラウドはオンプレミスより安全と言われるのか?

「リスクがあるなら、やっぱり自社ですべて管理した方が安心じゃないの?」
そう考える方もいらっしゃるかもしれません。しかし、多くのケースでその答えは「いいえ」です。
世界的な大手クラウド事業者は、私たちが想像する以上に、莫大な費用と最高レベルの技術力をセキュリティに投じています。
例えば、Amazon、Microsoft、Googleのような企業は、何兆円ものお金をかけて、世界中から優秀なエンジニアを集め、24時間365日、最新のセキュリティ対策を講じています。物理的なセキュリティ(警備員や監視カメラ)から、サイバーセキュリティ(ハッキング対策)まで、あらゆる脅威に備えています。
自社でこれと同じレベルのセキュリティ環境を構築し、維持するのは、ほとんどの企業にとって現実的ではありません。
英国国防省でさえ、「パブリッククラウドの方がオンプレミスよりも安全だ」という見解を公式に発表しています。なぜなら、クラウド事業者はセキュリティパッチ{ソフトウェアの脆弱性(セキュリティ上の欠陥)を修正するためのプログラムのこと}をより早く適用し、常に最新のセキュリティ機能を維持しているからです。
僕たち利用者は、この巨大な企業のセキュリティ対策の恩恵を、安価に享受できるというわけですね。
まとめ
今回は、クラウドの安全性と信頼性について、僕自身が学んだことを皆さんと共有しました。
- クラウドには様々なリスクがあるが、それはオンプレミスでも同じ。リスクはゼロにならないことを前提に、適切な対策を講じることが重要です。
- 多くのケースで、大手クラウド事業者のパブリッククラウドを利用する方が、自社で管理するよりも高い安全性を確保できます。
- 安全性を確保するためには、利用者側も「暗号化されているか?」や「バックアップは取っているか?」など、常に意識することが大切です。
今回の内容で、クラウドに対する不安が少しでも軽くなったら嬉しいです。IT業界に転生した僕も、日々新しい知識を吸収しているので、また皆さんに役立つ情報をお届けしたいと思います。
次回は、クラウドのメリットについて、さらに詳しく見ていきます!お楽しみに!

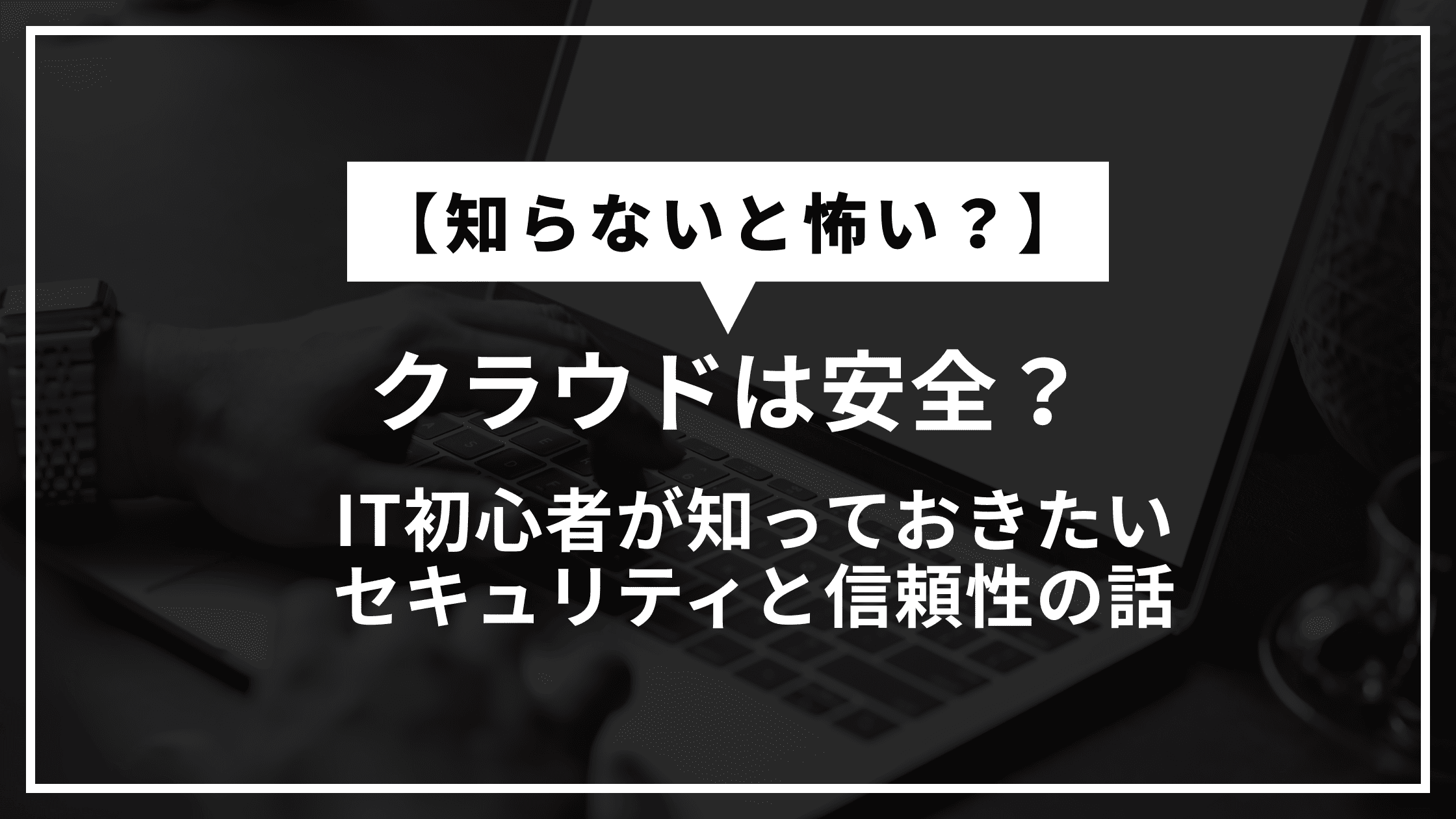
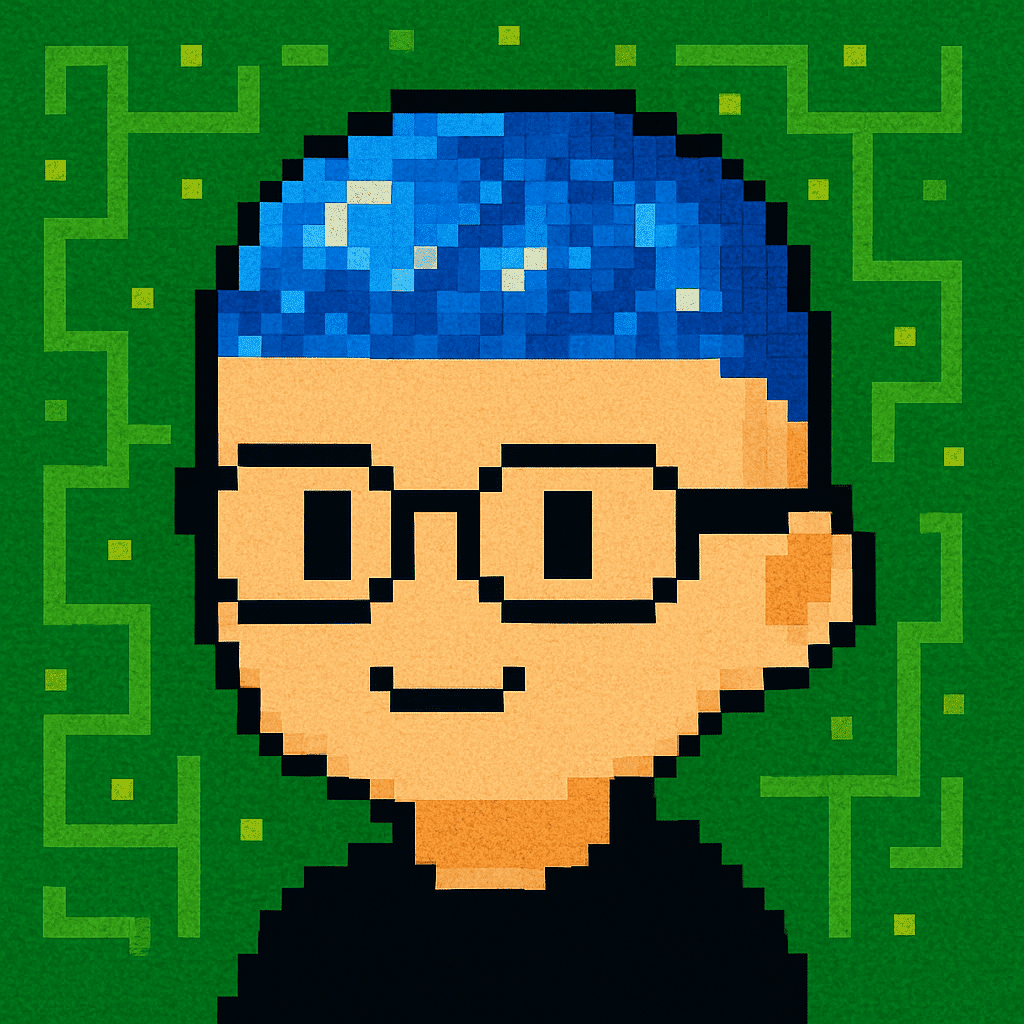

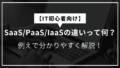
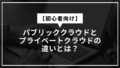
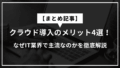
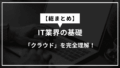
コメント