
ご安全に!瑠璃坊主です!
「機械系の俺がIT業界に転生してみた件」今回も読んでいただきありがとうございます。
これまで、クラウドがもたらす「経済性」「柔軟性」「可用性」「構築スピード」という4つの大きなメリットについて、お話してきました。
前回までのまとめ記事はこちら↓
【まとめ記事】クラウド導入のメリット4選!なぜIT業界で主流なのかを徹底解説
また、クラウドって何??って方はこちらのまとめ記事もどうぞ!↓
【総まとめ】IT業界の基礎「クラウド」を完全理解!
いよいよ今回のセクションから、これらのメリットがどのようにして実現されているのか、具体的なクラウドサービスの内容に入っていきます。
最初のテーマは、クラウドの基本中の基本である「ストレージサービス」です。 IT業界に転生した僕がUdemy、その他の講義で学んだ内容を、これまでの記事同様、IT業界未経験の昔の僕でも理解できるように、身近な例えを交えながら詳しく解説していきます。
1. クラウドのストレージサービスって何?

プラントエンジニアでパソコンをあまり勉強してこなかった僕にとって、ストレージと聞くと、会社に置かれていた物理的なサーバーや、パソコンの内蔵ハードディスクを思い浮かべていました。
クラウドにおけるストレージサービスとは、簡単に言うと、インターネット上にデータを保存したり、バックアップを取ったりするためのサービスを指します。
一番身近な例だと、GoogleドライブやDropboxのようなオンラインストレージサービスをイメージしてもらえると分かりやすいかもしれません。 スマホで撮った写真をGoogleフォトに保存したり、仕事のファイルをDropboxにアップロードしたりしますよね?それと同じように、クラウドのストレージサービスは、Webサイトの画像データや、動画、企業の重要なデータなどを保存するために使われます。
今回は、AWS(Amazon Web Services)が提供する代表的なストレージサービスである「Amazon S3(Amazon Simple Storage Service)」を例に、クラウドストレージのすごさを見ていきましょう。
2. クラウドストレージのすごい4つの特徴
Amazon S3は、2006年から提供されている、AWSの中でも最も歴史のあるサービスの一つです。このサービスは、「オブジェクトストレージ」という形式で、データを保存します。
オブジェクトストレージとは、データを「オブジェクト」という単位で管理する仕組みです。写真や動画、文書ファイルなど、どんな形式のデータでも、そのまま保存できるのが特徴です。データをファイル名やフォルダ名で管理するのではなく、固有のIDを付けて管理するので、大量のデータを効率よく扱うことができます。
このクラウドストレージには、オンプレミス{サーバーやソフトウェアなどのシステムを自社の施設内に設置・保有し、自社で運用・管理すること}では考えられないような、すごい特徴が4つあります。

① 驚異的な耐久性と可用性
ITの世界では、どんなシステムにも障害のリスクがある、という前提で考えます。データを保存するストレージも例外ではありません。だからこそ、「耐久性」と「可用性」という2つの指標が非常に重要になります。
- 耐久性(Durability):データが失われる可能性の低さを示す指標。
- 可用性(Availability):サービスが常に利用可能な状態であること。
Amazon S3は、データを世界中の複数のデータセンターに分散して保存することで、「イレブンナイン(99.999999999%)」という驚異的な耐久性を実現しています。これは、100億個のファイルを保存しても、1年間に1個失われるかどうか、というレベルです。 僕たちの身近なデータに置き換えると、例えば、あなたが10,000枚の写真を撮ったとします。それが100万回繰り返される、つまり100億枚の写真を保存しても、1年間で1枚失われるかどうかという確率です。
また、可用性も99.9%以上と非常に高く、滅多にサービスが止まることはありません。
これだけの高い耐久性と可用性を持つストレージを、自社で用意しようと思ったら、どれだけの費用と専門的な技術力が必要になるでしょうか?気が遠くなりそうですよね(笑)
クラウドなら、それを安価に利用できるんだから、本当にすごいことです。
② 実質、容量無制限
オンプレミスのサーバーにデータを保存する場合、容量が足りなくなったら、新しいハードディスクを追加したり、容量の大きなサーバーに買い替えたりする必要があります。
でも、クラウドストレージには、実質的に容量の制限がありません。 Amazon S3では、1ファイルあたり最大5TBという制約はあるものの、全体の容量としては無制限に使えるんです。
僕たちが利用しているGoogleドライブの容量が枯渇した、なんて話を聞かないのと一緒ですね。 必要な時に必要なだけ容量が自動で拡張されるので、残りの容量を気にする必要がありません。これにより、私たちは安心して、どれだけデータが増えても、気にすることなく保存できるわけです。
これは、特に写真や動画など、大容量のデータを扱うビジネスにとって、非常に大きなメリットとなります。
③ コストダウンと豊富なバリエーション

クラウドストレージは、使った分だけ支払う「従量課金制」が基本なので、非常に低コストで利用できます。 例えば、Amazon S3の最も一般的なクラスでは、1GBあたり月々0.023USD(約3.5円、1ドル150円換算)という安さです。
また、クラウドストレージは、コストや性能に合わせたさまざまな種類が用意されています。 中でも面白いのが、Amazon S3 Glacier(アマゾン エススリー グレイシア)というサービスです。
Glacierは日本語で「氷河」という意味のこのサービスは、データの読み出しに時間がかかる代わりに、驚くほど安価にデータを長期保存できます。システムのアクセスログや監査ログなど、頻繁に見る必要はないけれど、保管が必要なデータの保存に最適です。一番安いものでは、1GBあたり月々約0.15円という破格のコストで利用できます。
さらに、これらのストレージクラスの間で、データを自動的に移動させたり、不要なデータを自動で削除したりする機能も備わっているので、人的なミスを減らし、運用を効率化することもできるんです。
3. 知っておきたい!ストレージの種類と使い分け
一口にストレージと言っても、実はデータの用途によって最適な種類が異なります。 IT業界で働く上で、これらの違いを理解しておくことは非常に重要です。
- オブジェクトストレージ
- 特徴:データをオブジェクトとして保存する。耐久性が非常に高い。
- 用途:写真や動画、Webサイトの静的なデータ、バックアップデータの保存など。
- 代表的なサービス:Amazon S3
- ブロックストレージ
- 特徴:データをブロックと呼ばれる小さな単位で保存する。読み書きの速度が速く、サーバーのOSやアプリケーションの起動に最適。
- 用途:仮想サーバーの起動ディスクや、高い性能が求められるデータベースなど。
- 代表的なサービス:Amazon EBS(Elastic Block Store)
- ファイルストレージ
- 特徴:複数のユーザーやサーバーでデータを共有できる。普段僕たちが使っているファイルサーバーと同じ感覚で使える。
- 用途:オフィスで共有するファイルサーバーや、複数のサーバーで同じデータを共有する必要がある場合。
- 代表的なサービス:Amazon EFS(Elastic File System)
このように、クラウドでは、用途に応じて最適なストレージサービスを使い分けることで、コストを最適化し、パフォーマンスを最大化することができるんです。

このセクションの終わりに
今回は、クラウドサービスの中でも最も基本的な「ストレージサービス」について学びました。
- 驚異的な耐久性と実質容量無制限、そして低コスト。
- データの性質や用途に合わせて、最適なストレージを選択できる。
これまでの記事で学んだ「クラウドのメリット」が、実際のサービスでどのように実現されているか、少しずつイメージできてきたんじゃないかな。
次の記事では、いよいよIT業界の主役とも言える「仮想サーバー」について詳しく見ていこうと思います! 最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
それではご安全に!

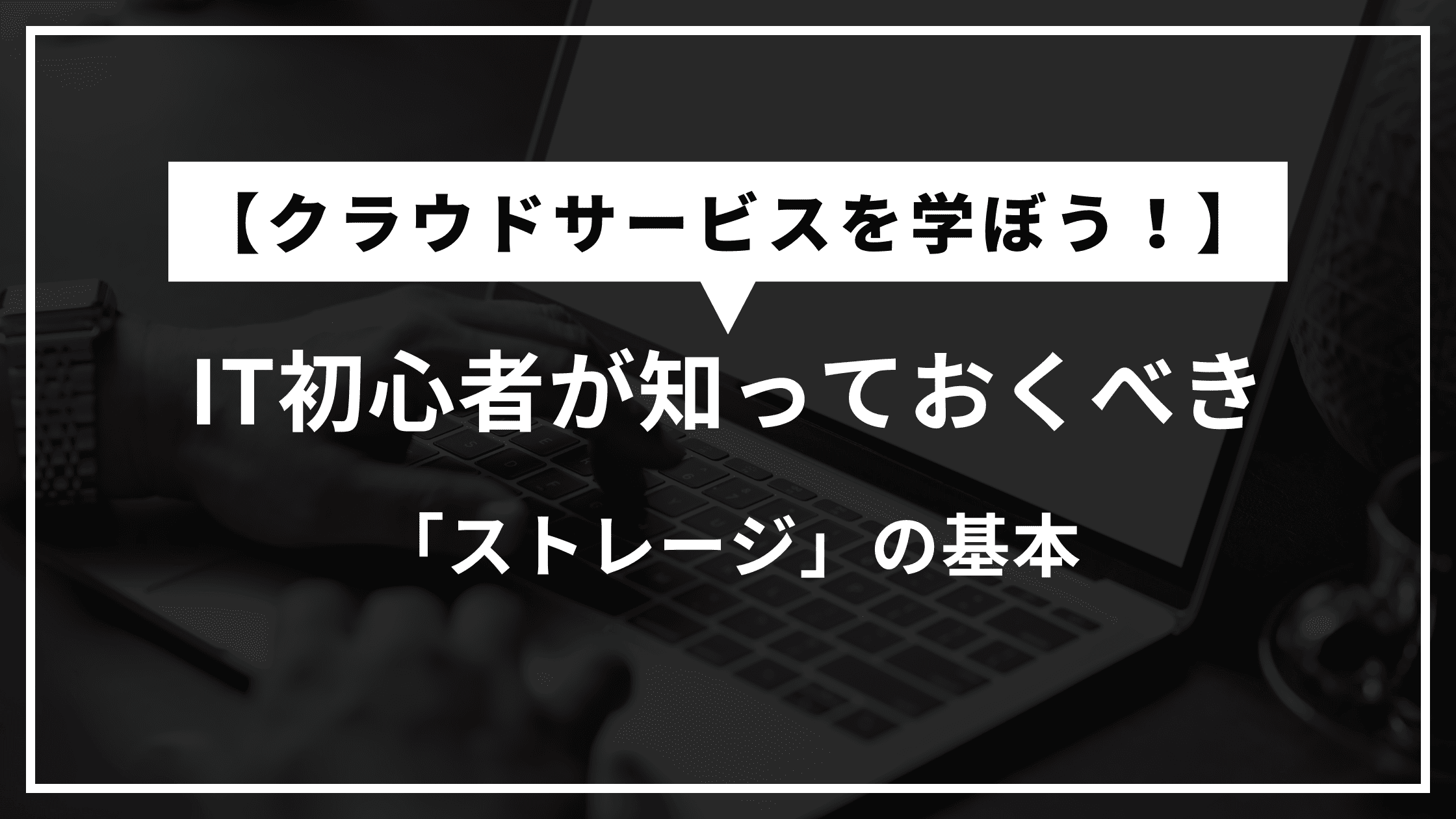
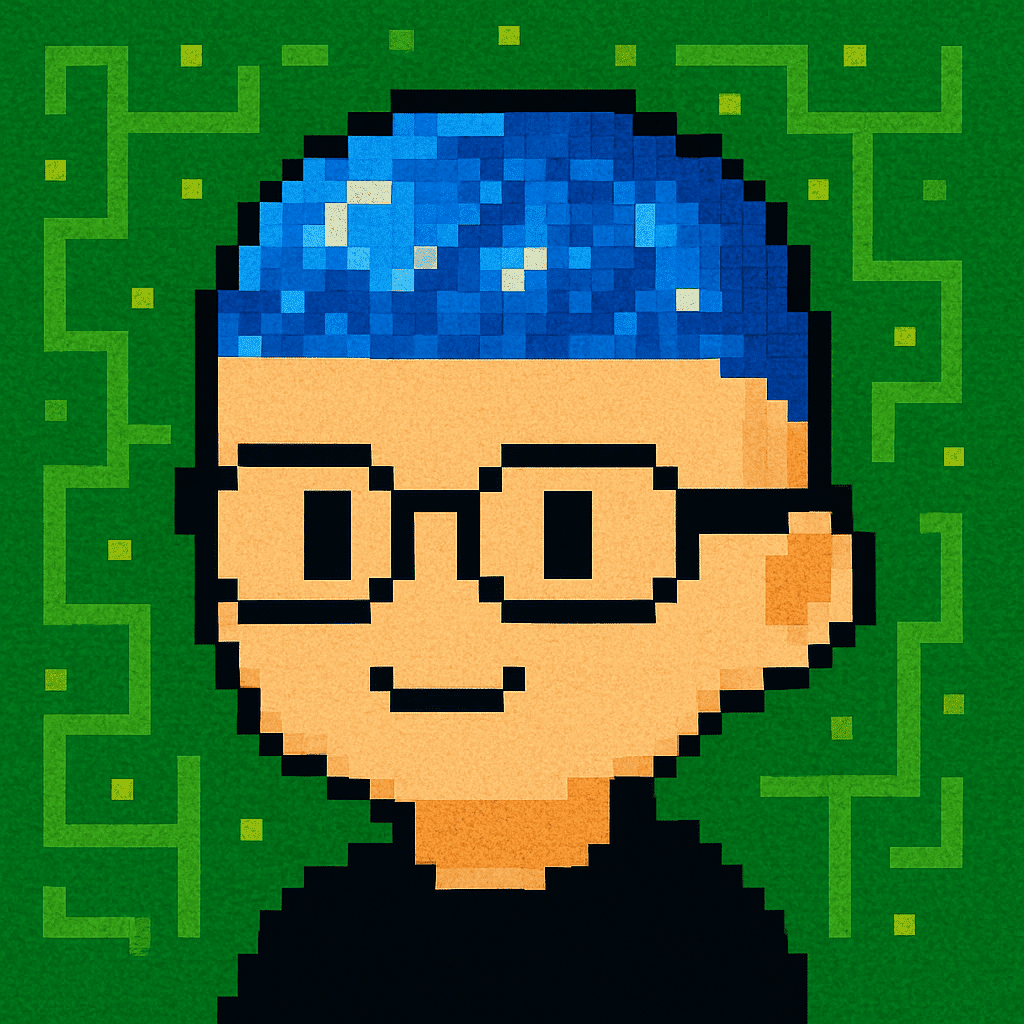
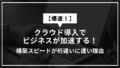
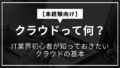
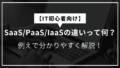


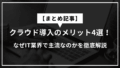

コメント